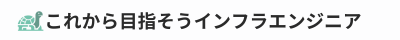【PR】この記事には広告を含む場合があります。
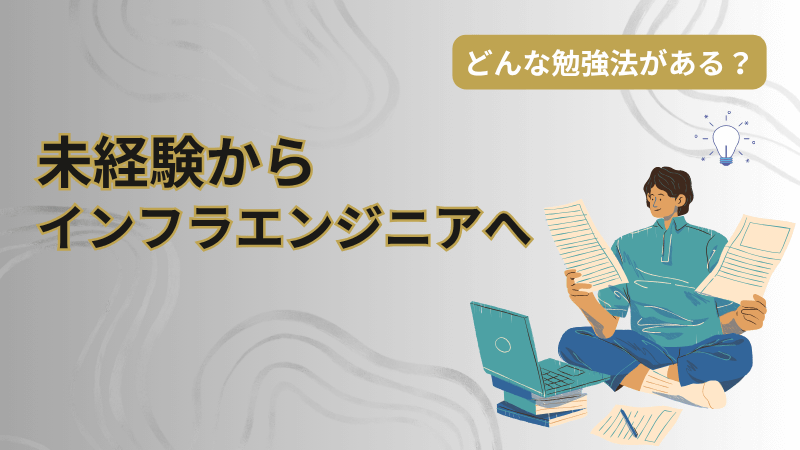
「インフラエンジニアを目指したいけど、未経験の自分に何ができるのか分からない…」
ネットワーク?サーバー?クラウド?
聞き慣れない専門用語や、どこから手をつければいいのか分からない状況に、最初の一歩が踏み出せずにいる方は少なくありません。
私自身も、IT未経験で右も左も分からない中、手探りで勉強を始めましたが、「やり方」さえ間違えなければ、ちゃんと道は開けます。
この記事では、未経験者のためのおすすめの勉強方法を目的別にわかりやすく解説します。
書籍・動画・ハンズオン・資格学習など、それぞれの特徴や進め方を実体験を交えつつ説明しています。
「自分にはどれが合いそうか」がきっと見えてくるはずです。

かつての私がそうだったように、この記事があなたの「最初の一歩」を後押しできたら嬉しいです。
「自分にもできるかも」と思えたその気持ち、大切にしてください。一緒に始めましょう。
インフラエンジニアとは?

インフラエンジニアは、システムの土台を設計し、構築して安定稼働させる専門職です。
ネットワークやサーバー、クラウドまで幅広く扱う役割があります。

縁の下で支える役です。
スマホでアプリが使える、Webサイトが表示される、といった“当たり前”の裏側を支えているのがこの仕事です。
- どんな仕事?
- なぜ注目されている?
- 筆者の実体験
どんな仕事?
インフラエンジニアは、システムの土台を設計・構築・運用・保守します。
具体的にはネットワークやサーバー、クラウドの管理を行います。
- 設計(環境構成図作成など)
- 構築(サーバー設定など)
- 運用・保守(監視や対応)
設計では、利用目的や負荷を考慮して構成図を作ります。
構築では物理機器やクラウド環境を、設計どおりに組み立てて設定します。たとえばAWSやオンプレミスでサーバーを構築したりします。
運用・保守では監視ツールで異常を検知し、トラブルがあれば原因を調べて対処します。
なぜ注目されている?
インフラエンジニアは今、多くの企業に必要とされる仕事です。
クラウドやリモートワークの普及で、システム基盤の整備が急速に進んでいるからです。
- クラウド導入の拡大
- リモートワークの増加
- ITサービスの普及
クラウドサービス(AWSやAzureなど)の導入が進み、それに対応できる人材が求められています。
また、働く場所を問わないリモートワーク環境でも、安定したネットワークとセキュリティが必須です。
こうした需要の増加により、未経験からでも学びやすい道が広がっています。
筆者の実体験
私はタッチタイピングはおろかパソコンもあまり得意ではありませんでした。
それでも「一生使えるスキルを身につけたい」という思いから、インフラエンジニアの勉強を始めました。
- 最初は専門用語に苦戦
- 仮想環境で実習を開始
- 初めてWebサーバー構築に成功
最初に「CentOSって何?」「仮想環境ってどう作るの?」と戸惑いました。
それでも本を読み、動画を見て、少しずつ知識を増やしていきました。
ある日、VirtualBoxにCentOSを入れて、Webサーバーを立ち上げたとき、ブラウザに「Hello World」が表示されたんです。
「自分の手で何かを動かせた!」という感動が忘れられません。
そこからさらにLinuxコマンドを学び、仮想環境で手を動かしては覚えるを繰り返していました。
「最初の一歩を踏み出す勇気」があれば、未経験でもインフラエンジニアを目指せると強く感じています。
未経験者におすすめの勉強方法【ジャンル別に解説】
未経験からインフラエンジニアを目指すには、効果的な学び方を知ることが大切です。
方法を知るだけで、不安が軽くなり、最初の一歩が踏み出しやすくなります。

自分に合う学び方を選べば、途中で挫折せずに続けられます。
- 書籍で学ぶ
- 動画で学ぶ方法
- 学習サイトを使う方法
- 仮想環境で実習する方法
- スクールに通う方法
- セミナーや勉強会で学ぶ方法
- 職業訓練を使う方法(離職中の方)
- 資格取得を目指す方法
書籍で学ぶ
本での勉強は、初心者が最初に全体像をつかむのに向いています。
書籍には、順を追ってインフラの知識を学べる工夫があります。
- 全体の流れをつかみ体系的に学べる
- くり返し読める
- 比喩や図解でやさしい説明が豊富
書籍の魅力は「体系的にまとまっている」こと。とくに初学者向けの本は、順を追って学べる構成になっており、理解の土台をしっかり作れます。
読んでわからない所は、付せんを貼って何度も読み返すのがコツです。
難解な専門用語も、イラストや比喩を交えて解説してくれる書籍が多く、安心して読み進められます。
動画で学ぶ(YouTube・Udemyなど)
動画は目と耳の両方を使って学べるため、理解しやすい学習方法です。
とくに初めて見る操作や設定を、画面付きで確認できる点が強みです。
- 操作の流れが見える
- スマホでも学べる
- スキマ時間を活用できる
「実際の画面を見ながら進められる」というメリットがあります。
スマホやタブレットでも見られるため、通勤時間や家事の合間などスキマ時間にも勉強できます。
動画は理解しやすいですが、受け身にならないように注意が必要です。
学習サイトで学ぶ
学習サイトは、無料ですぐに実践できる内容が多く、手を動かしながら覚えられます。
インフラの基本コマンドや設定を「クイズ」や「演習」で確認できるのが特徴です。
- 無料のサイトも多く学習環境を選ばない
- 自動で採点される機能がある
- 弱点を把握しやすい
たとえばProgateは、ブラウザ上でLinuxやネットワークの基本が学べます。
ドットインストールも、短い動画とスライドで基本操作をわかりやすく紹介しています。
またPing-tというサイトでは、資格試験に出る問題をクイズ形式で解けます。
「間違えた問題」が記録されるため、復習もしやすいです。
実際に手を動かして学ぶ(ハンズオン)
インフラの学習では、「読む」だけでなく「さわる」ことが大事です。
仮想環境を使えば、家にいながら安全に実習ができます。
- 実務に近い練習ができる
- 覚えるスピードが上がる
- 環境構築の力がつく
たとえばVirtualBoxとCentOSを使えば、パソコン内に仮想サーバーが作れます。
Cent OSをインストールし、基本コマンド(ls、cd、mkdir)を入力してコマンドライン操作を試してみましょう。
私は最初、仮想環境の設定で失敗しましたが、何度もやり直すうちに自然と理解が深まりました。
失敗は成長のきっかけです。仮想環境なら壊れてもやり直せます。
「実際に手を動かしてみること」が、何よりも記憶に残ります。
ITスクールを通して学ぶ
独学に不安がある人には、ITスクールの活用もおすすめです。
スクールには講師のサポートや就職支援があり、安心して学習を進められます。
- 質問できる環境がある
- 学習の道すじが決まっている
- 就職サポートもある
大きく分けてオンライン型とオフライン型(通学型)があり、講師が直接またはチャットで質問に答えてくれるので、疑問をすぐに解決できます。
学ぶ順番が決まっているため、迷わずに進めるのがメリットです。
ただしそれなりに費用は高めなので、無料体験や口コミもチェックしましょう。
勉強会、セミナーを通して学ぶ
勉強会やセミナーは、仲間と一緒に学びたい人におすすめです。
実際の現場で使われる知識やトレンドを、リアルタイムで吸収できます。
- 現場の情報が得られる
- 仲間ができて刺激になる
- 質問できる時間もある
無料または低価格のインフラ勉強会がよく開催されています。第一線で活躍しているエンジニアから実践的な技術や理論を学べる機会があります。
内容は、初学者向けのLinux講座から、最新のクラウド活用術までさまざまです。
会場では同じ目標を持つ人たちと交流でき、モチベーションが高まったり、人脈づくりに役に立ったりするかと思います。
ただし、開催地や時間が限られるので、オンライン開催も活用すると良いでしょう。
職業訓練などを活用して学ぶ(離職中の方)
転職や再就職を目指す人にとって、職業訓練は強い味方になります。
公的支援を受けながら、実務に近いスキルを身につけることができます。
- 無料または低価格で学べる
- 実務的な内容が多い
- 就職支援も受けられる
ハローワークを通じて申し込むことで、公共職業訓練や求職者支援訓練を受けることができます。
インフラエンジニアに関する現場で必要なスキルが学べる講座などがあれば積極的に申し込むと良いでしょう。
ただし、訓練の申し込み時期や地域により開講状況が異なるので、事前の確認が必要です。
資格の勉強を通して学ぶ
資格勉強は、学ぶ範囲が決まっているため、初心者にとって始めやすい学習法です。
学習のゴールが明確なので、モチベーションの維持にもつながります。
- 学習範囲が明確
- 就職で評価されやすい
- 教材が豊富にある
たとえば「ITパスポート」は、ITの基本を広く浅く学べる国家資格で、初心者向きです。
「LinuCレベル1」や「LPIC-1」は、Linux操作の基礎が問われる実践的な資格です。
また「AWSクラウドプラクティショナー」は、クラウドの基礎知識を学べる初級資格です。
動画解説やSNSでの学習記録も組み合わせると、理解が深まり、モチベーションも続きます。
まとめ:勉強方法は一つじゃない、自分に合ったやり方を探そう
インフラエンジニアを目指すには、たくさんの学び方があります。
本、動画、実習、資格など、それぞれに強みがあります。

無理せず、自分に合う方法を選べば、誰でも始められます。
- 本で学ぶ
- 動画で学ぶ
- 学習サイトを使う
- ハンズオンで体験する
- スクールを活用する
- 勉強会で刺激を受ける
- 職業訓練を利用する
- 資格取得で自信をつける
私が実践した流れは、「動画で理解→本で補足→仮想環境で実践→資格で知識整理」です。
どこから始めても大丈夫です。まずは「これならできそう」と思える方法を一つ選んでみましょう。
Q&A
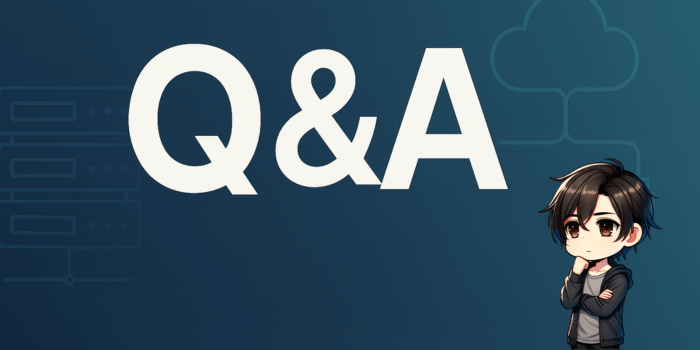
Q:インフラエンジニアってどんな仕事?
インフラエンジニアは、ネットワークやサーバー、クラウドなど、システムの土台を設計・構築・運用・保守する専門職です。スマホアプリが使えたり、Webサイトが表示されたりする“当たり前”の裏側を支える仕事です。
Q:どうしてインフラエンジニアが注目されているの?
クラウドの普及やリモートワークの拡大により、システム基盤の整備が急速に求められています。そのため、クラウドやセキュリティに強いインフラエンジニアの需要が高まっています。
Q:未経験でもインフラエンジニアを目指せる?
はい、未経験からでも目指せます。最初は専門用語に戸惑うかもしれませんが、動画や書籍、仮想環境での実習などを通じて、少しずつスキルを身につけることができます。
Q:未経験者におすすめの勉強方法は?
自分に合った方法を選ぶのがポイントです。たとえば、「本で全体像をつかむ→動画で実際の操作を学ぶ→仮想環境で手を動かす→資格取得で知識を整理」といった流れがおすすめです。
Q:資格は取得したほうがいい?
資格は学習範囲が明確で、初心者でも始めやすい学び方です。ITパスポートやLinuCレベル1、AWSクラウドプラクティショナーなどの初級資格は、就職活動にも役立ちます。ただし必須というわけでもありません。